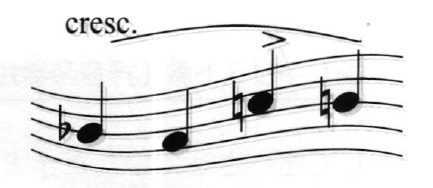2022年・松山大会のご案内
東京と地方とで交互に開いてきたキリスト教礼拝音楽学会大会、ことしはいよいよ四国での開催となりました。会場の日本基督教団松山教会は、1879(明治 12)年、組合教会により伝道開始され、1885(明治18)年に創立された、松山で最も歴史の古い教会です。1880年創立の松山女学校(現・東雲学園)、1891年創立の松山夜学校(当初の名称は「普通夜学会」、現・松山学院)とも深いつながりがあります。
1903年版(明治版)賛美歌に収載された日本人作賛美歌中、最もよく知られ、現代の賛美歌集にまで継承されている「山路越えて」の作詞者、西村清雄[にしむら・すがお(1871-1964)]は、松山教会の会員であり、松山市名誉市民第3号となった教育者です。松山生まれの西村清雄は10代でキリスト者となり、貧困層の子どもたちのため、宣教師コーネリア・ジャドソンと共に「普通夜学会」を開設、21歳で初代校長となります。(その後、普通夜学会は松山城南高等学校となり、現在は松山学院高等学校と改称、キリスト教教育を継承しています。) 1903年2月、西村が愛媛県南部の伝道応援に赴いた帰途、山道を一人徒歩でたどりながら創作したのが「山路越えて」です。作歌地に近い法華津峠(ほけつとうげ)には、さざ波がきらめく宇和海を見晴るかす一番眺めの良い場所に、歌詞を刻んだ石碑が建てられています。60年以上の間、松山で教育に献身し、非常に個性的、魅力的な人物であった西村と彼の賛美歌については、上島一高[かみじま・かずたか]氏(日本基督教団松山教会牧師)が、今回ご講演下さる予定です。
日本におけるプロテスタント伝道黎明期、徳川による鎖国が解けると同時に、欧米の様々な宣教団体が、伝道の情熱に燃える宣教師を日本各地に派遣しました。メソジスト、バプテスト、聖公会などの大教派だけではなく、小教派の宣教師も大勢来日しました。交通手段の十分でない時代であったにもかかわらず、都市部を避け、あえて伝道困難な地方へと入っていった小教派も少なくありません。1887(明治20)年に北米で活動をスタートしたアライアンス教会も、1893(明治26)年に創立者 A・B・シンプソン(1843-1919)が来日し、日本伝道を始めました。来日した多数の教派の中で、16番目の伝道開始とされています。西日本に焦点をあわせ、他教派が働いていない未伝地の一般大衆に重点を置いて伝道を進めました。当初、中国山地の奥深く、広島県三次に1895(明治28)年、本部を設置。その後1899(明治32)年に広島市部へ移転し、現在も広島が本部となっています。「同盟系」として知られるヨーロッパ源流のアライアンス教会(スカンジナビアン・アライアンス)とは異なる、北米源流の教会で、英語名は “The Christian and Missionary Alliance”です。戦前は「日本協同基督教会」と称していました。第二次世界大戦中の日本基督教団への合同を経て、戦後1949年に日本アライアンス教団再建。再建後も日本基督教団に残留した教会が多くありましたが、現在、全国のアライアンス教会数は約 40。広島に 12、愛媛には13 の教会が存在しており、その他、千葉以西の全国に教会が散在しています。広島、愛媛の教会を中心にしたグループであるため、全国的にはほとんどその存在を知られないまま、1世紀以上、地方での伝道を黙々と担い続けています。実はアライアンス創立者 A・B・シンプソンは、多数の賛美歌を遺しています。シンプソンは、ニューヨーク13番街長老教会牧師、名説教家としての生活の中で深い霊的渇望を抱き、キリストの内住による霊的満たしと海外伝道への関心が信仰を生き返らせることを経験します。それを分かち合う集まりが次第に大きくなり、世界的な宣教団体へと育っていったのです。シンプソンは多数の詩を書き、説教の中でも朗読し、やがて曲がつけられて賛美歌となってゆきましたが、後には自身で旋律も付すようになりました。日本では1954年版『讃美歌』497番「あめなる日月 [ ひつき ] は」が、おそらく最も良く知られたシンプソンの賛美歌でしょう。いわゆる福音派系の賛美歌集には彼の賛美歌が複数収載されてきました。『新聖歌』(2001年初版、日本福音連盟、教文館)の巻末索引には、7曲が挙げられており、『教会福音賛美歌』(2012年初版、福音讃美歌協会)には2曲が収められています。また、アライアンス宣教師団体は 2 冊の賛美歌集を発行していますが、そこには多数のシンプソン作賛美歌が見られます。『勝利の歌 I』(1959年初版、いのちのことば社)には9曲、『勝利の歌 II』(1964年初版、いのちのことば社)には11曲、合計20曲です。こうした、これまでいわゆる主流教派の教会では認知されてこなかったアライアンス教会の四国伝道の歴史とシンプソン作の賛美歌について、今回は、後藤一都[ごとう・かずと] 氏(日本アライアンス教団北条希望の丘教会牧師)に講演していただきます。
四国の教会は多くが小規模です。明治期、日本最大の教会として知られ、数百人の礼拝出席者が集った日本基督教団高知教会、組合教会の拠点の一つであった日本基督教団今治教会等、歴史的な大教会がいくつかあるほか、主要な市に現在も100人規模の礼拝出席のある教会が存在しますが、四国全体でみるとそれは例外と言ってよいでしょう。100年を越える歴史をもちながら、定住牧師もおらず、教会員数人という教会も決して珍しくありません。小教会での礼拝用楽器は、多くの場合リードオルガンです。日本基督教団四国教区は、教育部の予算でリードオルガン修復の技術者を毎年四国にお迎えし、修理・調整を希望する教会を巡回していただくことを、もう30年も続けています。技術者の交通費・滞在費は教育部が負担、各教会は修理・調整の実費のみ支出、二種教会(小規模教会)には修理・調整費用にも一部補助があります。他の教派の教会や個人の修理依頼も、メインの教団教会巡回予定の中で可能な限り対応していただきます。おかげで、四国内各教会の礼拝用リードオルガンの状態は安定しており、オルガンのための積立金を教会会計の中に準備している教会も少なくありません。礼拝用楽器の維持管理は、礼拝音楽にとっては大変重要なことですが、近くに技術者がいない地方の小規模教会にとっては、単独で実施するには困難な現実があります。教区で十分な予算を確保し、小教会への補助金も用意して教区内全教会に礼拝用楽器修理・調整を呼びかけている四国の例は、貴重です。これまでの30年の歴史の最初から約20年間、お一人で四国を巡回して下さった和久井輝夫[わくい・てるお]氏(工房和久井、長野県須坂市)に、四国内の様々な教会を実際に訪れ、礼拝用楽器を調整する中で経験され考えてこられたことを、率直にお話しいただく予定です。10年ほど前からは、和久井さんの四国巡回のお働きは、ご子息の和久井真人[わくい・まこと]氏に引き継がれています。
日本基督教団松山教会礼拝堂は、会衆席220。天井が高く、永田音響設計によりオルガンに相応しい響きに整備されています。設置されているオルガンは、1996年テイラー&ブーディー社製二段手鍵盤・足鍵盤・22ストップ。林佑子氏のアドバイスによる楽器で、電動送風と足踏みふいごによる送風のいずれかを選択できることが特徴です。オルガンが設置されている中二階ギャラリーに、巨大なふいごが置かれているのを見ることができます。今次大会の開会は、このオルガン奏楽によるメディテーションです。会場教会のオルガニストの高井郁代[たかい・いくよ]氏がご協力くださいます。
一方、大会の閉会は、四国の伝道の歴史に由来する二台のリードオルガンによる奏楽をお聴きいただきます。1台は39鍵のミキ・ベビーオルガンで、オルガン内部に1936(昭和11)年の保証書が貼ってあります。第二次世界大戦前、高知市内で教会開拓、路傍伝道に使われたものです。開拓伝道された教会は、戦後は日本キリスト改革派教会となっています。小さなオルガンですが、ドイツ製のリードが内蔵されており、味わい深い音色です。ミキの39鍵ベビーオルガンは、国内で数台しか確認されていません。もう 1 台はアライアンスの米国人宣教師メーベル・フランシス(1880-1975)が使用していた39鍵のメイソン&ハムリン社製で、金魚型と称されるベビーオルガン。昨年、和久井真人氏によって修復されたばかりです。フランシスは 1909(明治 42)年に来日、続いてフランシスの弟とその妻、フランシスの妹も宣教師として来日、姉弟4人が日本の教会のために献身しています。フランシスは1965(昭和40)年に妹と共に帰国するまで56年間日本の教会と共に歩み、宣教師が一斉に帰国した大恐慌期も第二次世界大戦中も日本にとどまりました。大戦中は妹と共に東京、横浜に強制収容され、米軍機の来襲時には思わず「敵機だ!」と叫んだことが伝えられています。松山で46年間在住、「愛の人フランシス」として教会内外の大勢の人の敬愛を受け、松山市特別名誉市民第2号とされています。現在、この愛らしいオルガンは、フランシスらが創設した松山のぞみ幼稚園で大切に保管されています。
以上、東京から遠く離れた四国での開催ということで、開催地に関わる大会プログラムを詳細にご案内してまいりました。例年の大会同様、会員による意欲的な発表も2本予定されております。四国は域内にある寺を巡礼する、八十八箇所参りの地として知られます。日常生活の場を離れ、一歩一歩足を動かしながら祈りの場を巡ってゆく人の心にはどのような風景が拡がり、歌が生まれているのでしょうか。私たちの会も巡礼の地、四国で、それぞれの礼拝への思いを豊かにし、新たな気づきと実践への深い促しをうけとることができますように。
大会副主題に掲げた「信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐」ということばは、敬愛する北村宗次牧師の愛唱聖句です。様々な意味で厳しい状況にある地方教会に集い、教会を支え、信仰の歩みをたどり続けている名も無き信仰者の姿が、このことばの中にすけて見えてくるような気がします。松山教会でぜひお目にかかりましょう。
四国大会実行委員 中村 証二
![]()